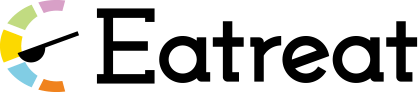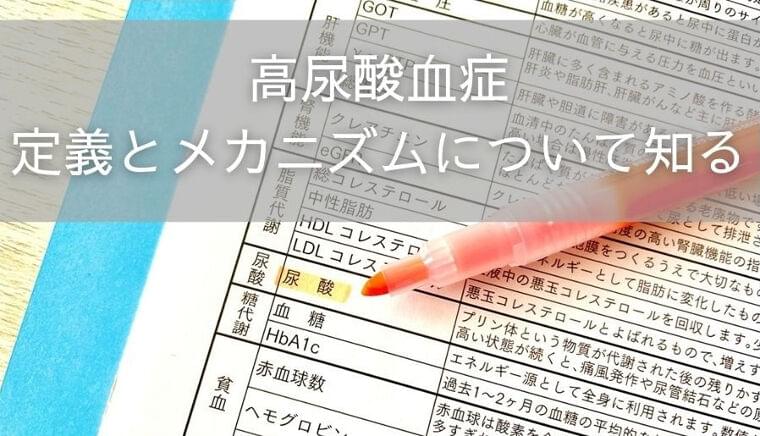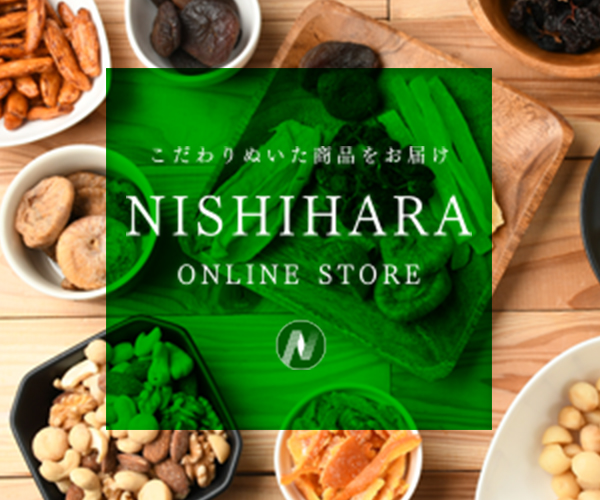前編では、新たな症候群「FUS」の定義や課題、リスクについて解説しました。
後編では、FUSの原因、対処法、今後の方向性についてお伝えします。
FUSの原因
身体的特性や社会的要因、心理的要因が複雑に絡み合っていますが、大きく3つに分けることができます。
① 体質性痩せ
痩せ願望や摂食障害、過度な運動はないものの、低体重状態が持続する体質的特性のことを指します。体重は増えにくいですが、内分泌機能や月経周期は正常に保たれていることが多いです。
② SNS、ファッション誌などのメディアの影響による痩せ志向
メディアによる影響で「痩せ=美」という価値観が浸透しています。特に若年女性において理想の体型を求めるあまり、過度な食事摂取制限、偏った食生活を招いてしまうことがあります。
③ 社会的経済的要因・貧困などによる低栄養
貧困を背景に十分な食事を得られず、結果的に低BMIや低栄養状態に陥るケースも報告されています。
FUSの対処法と今後の方向性
原因に応じた個別的なアプローチと社会・教育レベルでの包括的な介入の両面が必要と考えられます。
① 体質性痩せへの対応
体質性痩せにも骨密度低下のリスクが指摘されているため、健康診断などでの骨密度測定や血液検査の実施が推奨されます。また、意図的に食事摂取制限をしていない場合でも、摂取量が少なく、栄養素不足になっている可能性があるため、栄養指導の実施も望ましいです。
② 痩身志向者への対応
正しい理解を促進するために、学校教育におけるボディイメージ教育やヘルスリテラシー教育の中で、以下の項目を重点的に取り入れることが推奨されます。
・適正なボディイメージの形成と体型の多様性に対する理解
・メディア情報を適切に評価・活用する能力の育成
・過度な痩身行動が引き起こす健康リスクについての理解促進
・バランスの良い栄養摂取の重要性と欠食が及ぼす健康問題への理解
月経周期異常や骨密度低下などの健康リスクについては、体質性痩せの対応と同様に、健康診断などでスクリーニングを行い、専門家が連携することによって早期診断・介入を行う体制作りが必要です。
③ 社会・経済的要因への対応
個人の努力だけでは解決が困難な場合があり、社会構造的な支援や政治的施策が必要です。
自治体や社会福祉団体による支援を拡充し、フードバンクの活用やこども食堂といった栄養バランスの取れた食事提供の場を増やすことが求められています。
今後の方向性
▶ガイドライン策定
身体症状、骨量測定、月経、栄養評価などを含む統一的なスクリーニング項目を設定し、診断基準を明文化する必要があります。そのためには、エビデンスとなりうる研究が求められています。
▶健診制度への組み込み
特定保健指導や職域健診などのように、FUSスクリーニングを含めた追加的な測定や介入を行う仕組み作りが必要です。特に骨量低下に対する早期の発見や介入は女性のライフコース全体に関わるため、極めて重要です。
▶教育・産業界との連携
小中高等学校の保健体育や大学生向けの健康啓発の場において、正しい食習慣を学び、適切なボディイメージを獲得する機会の拡充が求められています。
まとめ
2回にわたりFUSについて紹介してきました。
FUSの原因は個人だけでなく、社会的要因とも関連しているため、各現場で活躍する管理栄養士がFUSを理解し、対策に貢献することが求められます。
参考文献
・一般社団法人 日本肥満学会 「学術情報 女性の低体重/低栄養症候群(Female
Underweight/Undernutrition
Syndrome)(FUS)ステートメント(2025年4月17日公開)」
学術情報:日本肥満学会/JASSO (閲覧日:2025年7月1日)
関連コラム
・新たな症候群「FUS(女性の低体重/低栄養症候群)」を解説!~前編~