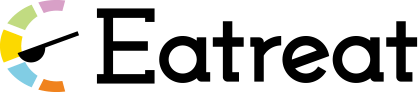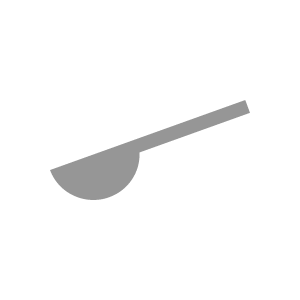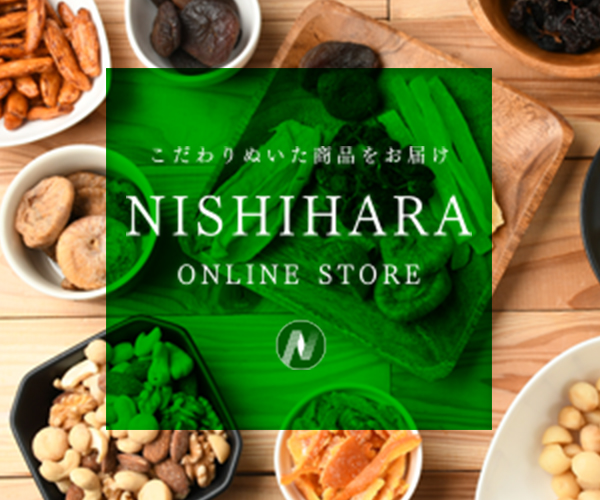送信完了しました!
あなたが投稿した記事を削除しました。
あなたが投稿した相談を削除しました。
回答を締め切りました。
あなたが投稿した意見(コメント)を削除しました。
あなたの予定1件を削除しました。
クリップボードにコピーしました。
計算結果をブログや他サイトで紹介するには
コピーボタンを押して右のタグをブログや他サイトにHTMLタグとして貼付けてご利用ください。 大きさを変更したい場合は、タグ内の「max-width:400px;」の数字を変更することで、 お好みの大きさに変更できます。例)max-width:510px;
マイ食品1件を削除しました。
マイ食品1件を削除しました。
公式食品1件の終売状態を変更しました。
公式食品1件の終売状態を変更しました。
不正解をリセット
不正解の問題だけリセットしますか?
回答を全部リセット
全ての回答をリセットしますか?