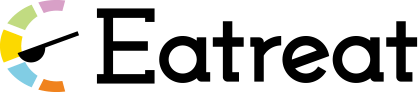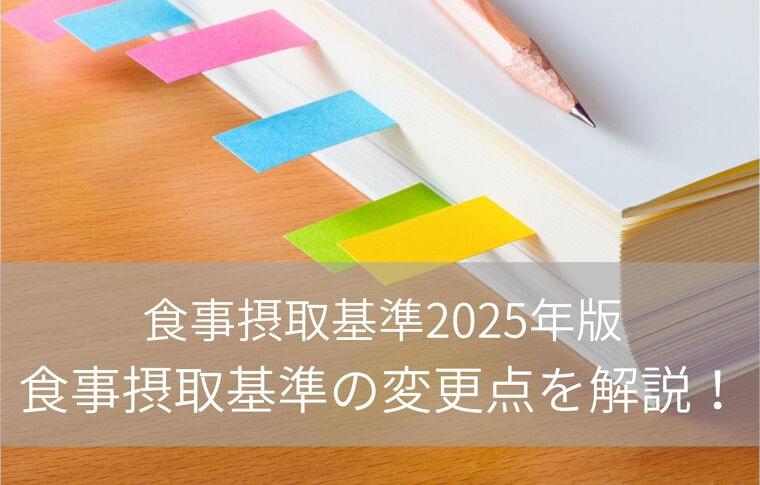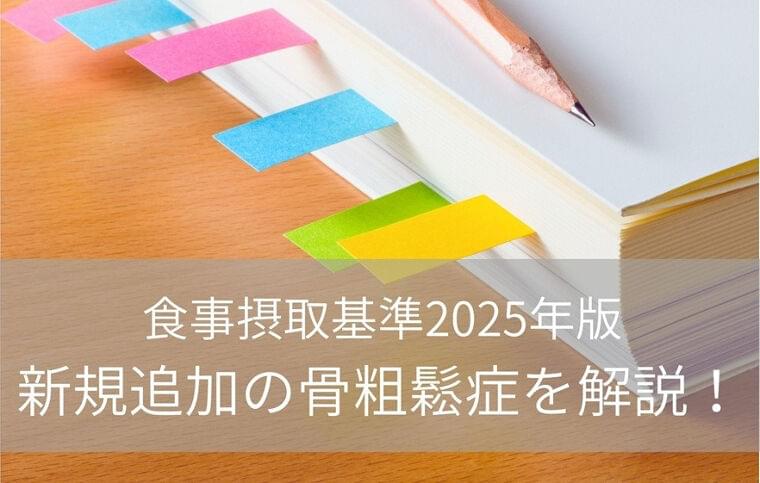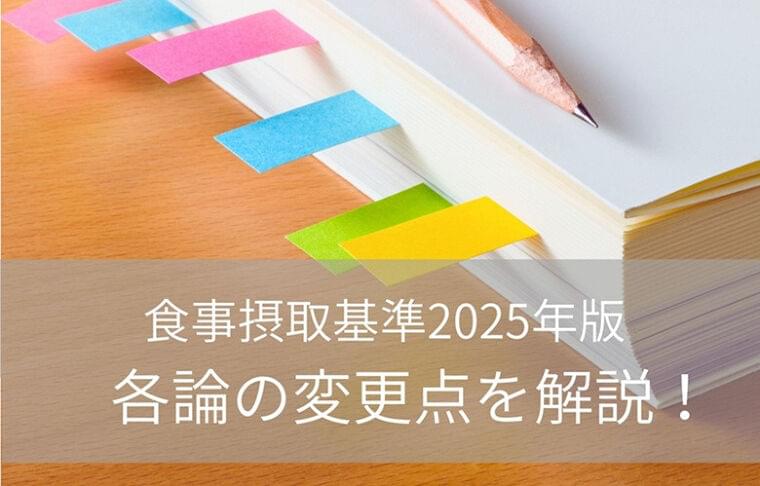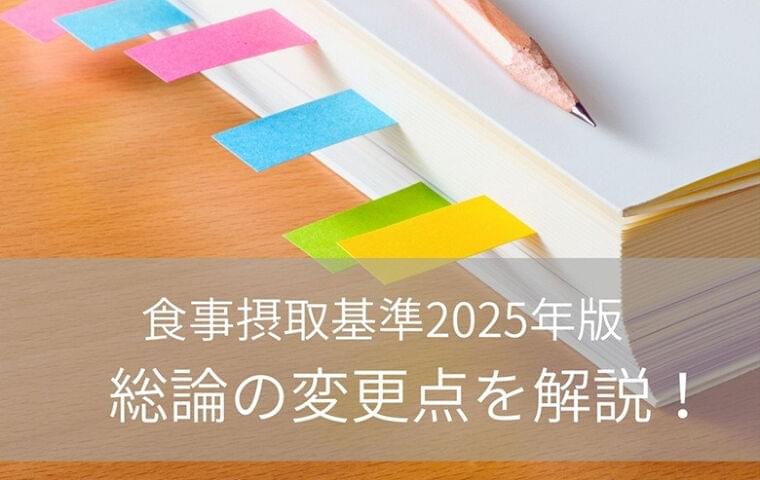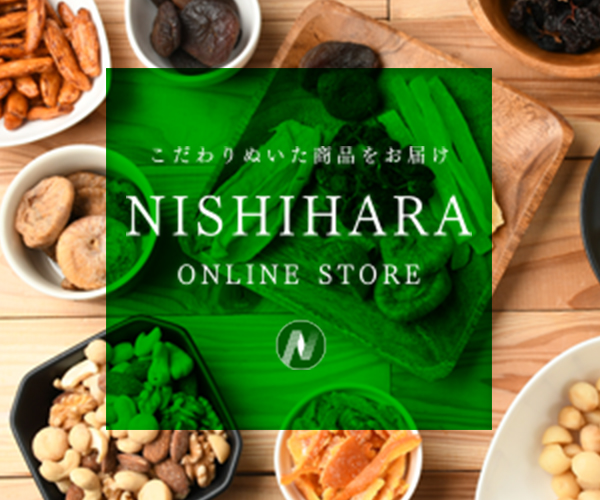これまでの2回では、日本人の食事摂取基準(2025年版)の主な変更点について総論、各論にわけて解説してきました。
3回目では、2025年版各論の「生活習慣病及び生活機能の維持・向上に係る疾患等とエネルギー・栄養素との関連」へ新たに追加された骨粗鬆症について、エネルギー・栄養素摂取との関連を解説します。
カルシウム
「十分なカルシウム摂取量は骨量の維持に必要であり、カルシウム摂取量が少ないことは低骨量のリスク因子になるといえるが、中高年においてカルシウム摂取量を増やしても、骨密度の低下や骨折を予防する効果は小さいと考えられる。」とのことです。
また「主にサプリメントを用いた介入研究は多いが、特に1000mg/日以上のカルシウムサプリメントを用いた場合にも心筋梗塞のリスク上昇が報告されている。これに否定的な見解もあるものの、特に1000mg/日以上のカルシウムサプリメントの使用は慎重になるべきであろう。」ということから、最近ではサプリメントを定期的に使用されている方も多いため、対象者の方に適宜確認する必要がありそうですね。
ビタミンD
「ビタミンDの栄養状態として、血中25-ヒドロキシビタミンD濃度を20ng/ml以上に保つことは、骨粗鬆症の予防の観点から重要と考えられる。しかしながら、サプリメントによる介入研究の結果を含めても、ビタミンDの付加による骨粗鬆症リスクの低減効果については、今後の検証が必要である。体内のビタミンDの維持のため、食事からの摂取を行うとともに、適切な日光暴露を図ることが望ましい。」とのことから、サプリメントの効果は今後検討が必要そうですが、ビタミンDを多く含む食品(鮭、いわし、さんま、キノコ類など)を摂取したり、適度な日光浴が好ましいようです。
たんぱく質
「たんぱく質の摂取量の不足の回避は不足であるが、現時点では骨粗鬆症の予防の観点から、たんぱく質摂取量の影響の程度について一定の結論を出すことは難しい。」とのことから、今後研究データの蓄積により新たな見解が出る可能性があると思われます。
エネルギー(体格)
「骨粗鬆症の予防、骨折リスクの低減のために低体重は回避するべきと考えられる。一方で、BMIが25kg/m2以上における骨折リスクについては、部位や性別によって異なると考えられるものの、おおむね低いと考えられる。しかしながら、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脂質異常症などに関連することから、過体重・肥満は推奨できない。」とのことから、骨粗鬆症や骨折のリスクが低減するからと言って、過体重や肥満はおすすめできなさそうですね。
その他のビタミン
「現時点ではビタミンCの積極的な摂取と、骨粗鬆症の予防については不明な点が多い。また、ビタミンK投与の臨床試験においては椎体骨折リスクの低減効果は認められておらず、骨粗鬆症の予防のためにビタミンKの積極的な摂取を勧める根拠はない。」とのことから、今後研究データの蓄積により新たな見解が出る可能性があると思われます。
参考文献
・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
関連コラム
・②骨粗しょう症 | 骨強度の低下を特徴とし骨折のリスクを増大しやすくなる疾患への対策
・高齢者と骨粗鬆症 前編