
管理栄養士・栄養士の皆さんが日々の業務で向き合う「栄養価計算」。献立作成やレシピ開発に必須のスキルですが、「これで合っているのか?」と不安になったり、特定の食品の扱いに迷ったりすることはありませんか?Eatreatの相談室でも、栄養価計算に関するご質問が数多く寄せられます。そこで今回は、特に業務経験の浅い方や、改めて基本を確認したい方に向けておすすめのコラムを5つピックアップしました。ぜひ、日々の業務にお役立てください。
まずは栄養価計算の全体像を知る
そもそも栄養価計算とはどういったものなのか、料理を栄養価計算するときにどのような手順で行うのかを抑えておきましょう。こちらのコラムでは、基本的な栄養価計算の流れや注意すべきポイントがまとめられています。
栄養価計算とは? 基礎をまるわかり解説!①
豚肉は大型?中型?食品選びに困ったときに読みたい!
栄養価計算でつまづきやすいのが、食品項目の選び方。特に、肉類は種類がたくさんあり、どれを選べばよいか悩んでしまうことも多いのではないでしょうか?こちらのコラムでは、「牛肉」「豚肉」「鶏肉」の選び方を丁寧に解説しています。また、野菜の中でも間違えやすい食品の一つとして「かぼちゃ」についてもご紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。
選択を間違えやすい食品を食材群別に紹介② 栄養価計算の疑問を解決!
食品成分表に該当するものがないときはどうする?
2025年8月現在、最新の食品成分表は「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」で、収載されている食品数は2,538食品となっています。かなり膨大な量ですが、それでも掲載されていないケースも少なくありません。食品成分表に掲載されていない食材を計算する場合はどのように対応すればよいのでしょうか?こちらのコラムでいくつかの方法を解説していますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
栄養価計算の疑問を解決!食品成分表に掲載されていない食材の計算方法は?
糖質を計算するにはどうする?
健康志向の高まりを受け、レシピ開発などで糖質の栄養価計算を求められるケースが増えています。八訂で炭水化物が細分化されたことで、計算に悩んだことがあるかもしれません。こちらのコラムでは、炭水化物や糖質について、栄養価計算の視点から詳しく解説しています。
【炭水化物と糖質】栄養価計算ではどの数値を選択する?
揚げ物を計算するときに抑えておきたい「吸油率」
唐揚げや天ぷらなど、揚げ物のレシピを作成する際に必ず使う「油」。油の量をどのように栄養価計算に反映させればよいか、悩んだ方もいるかもしれません。そんなときに使うのが「吸油率」という考え方です。この吸油率は、衣の有無や食材によって異なります。こちらのコラムでは、吸油率を使った栄養価計算の例や料理による吸油率の違いなどを詳しく解説しています。参考にできる書籍も紹介していますよ。
栄養価計算のよくある疑問を解説!②
参考文献
・文部科学省:「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」、文部科学省、
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html、(閲覧日:2025年8月15日)
関連コラム
・栄養価計算の疑問を解決!成分項目の選び方は?
・栄養価計算での「煮汁・漬け汁」の考え方を徹底解説
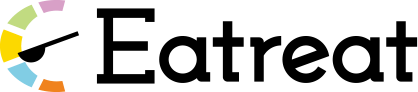




















![給食センターで火災、小中5校で食パン・ゼリーなど代替給食に 佐賀 [佐賀県]:朝日新聞](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/eat-treat.jp/up/w200/news/11511/11511_eae12d849e0492520dcd4761bfaa1c28.jpg?_t=1772173294)


