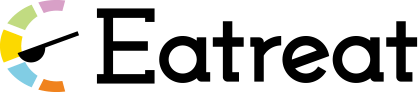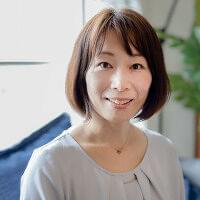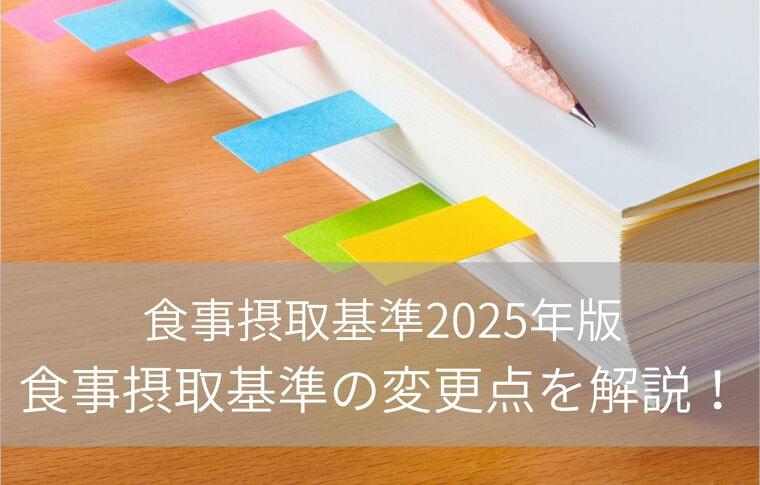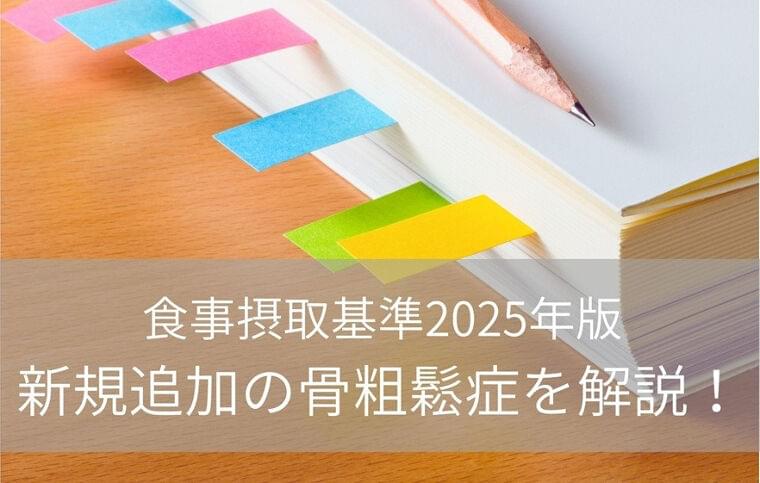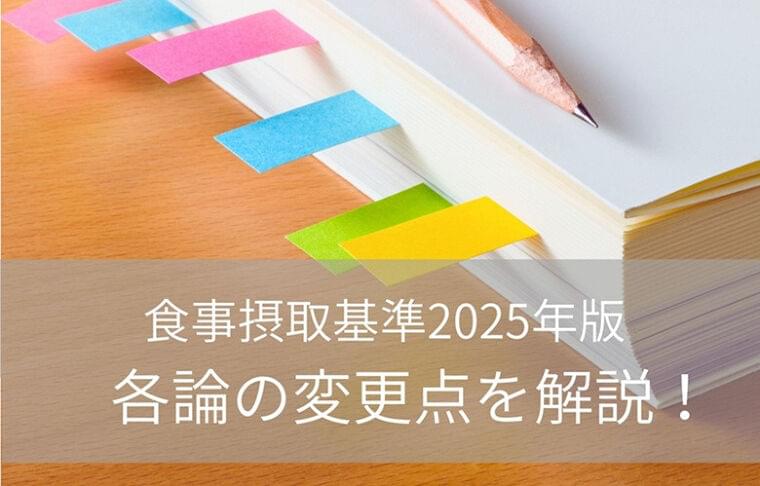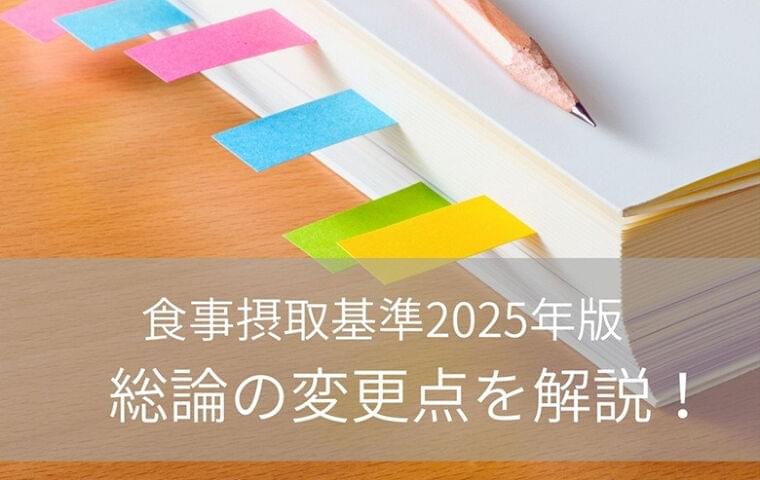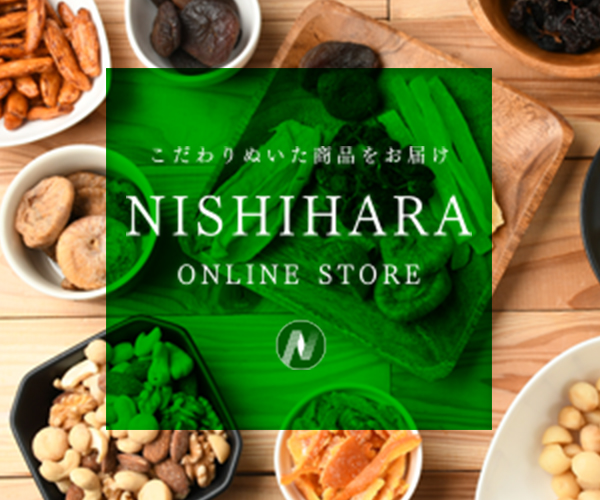指導・監査・診療報酬
2024.06.07
健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023を解説
【解説】健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 ~おさえておきたいポイント編~
前回のコラム では、健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023の概要についてご紹介しました。今回のコラムでは、管理栄養士・栄養士としておさえておきたいポイントについてご紹介します。
筋力トレーニングが新たに追加
国際的な身体活動ガイドラインの策定のために実施されたレビュー(主に介入研究)において、筋力トレーニング(筋トレ)により、筋力、身体機能、骨密度が改善し、高齢者では転倒や骨折のリスクが低減することが示されました。そのほか、筋トレの実施により、総死亡、心血管疾患、全がん、糖尿病の発症リスクが低下するなどの根拠が示され、新たに筋トレが推奨事項として追加されました。また、ウォーキングなどの有酸素運動と組み合わせることで、さらなる健康増進効果が期待できると考えられています。▶筋トレの種類 ▶推奨されるライフステージ ▶筋トレのポイント
全身持久力の新たな基準値が改訂
全身持久力の指標に最高酸素摂取量(VO2 peak/kg) があります。これは、より厳密に測定される最大酸素摂取量(VO2 max/kg)と同様、さまざまな要因による死亡や疾患発症の強力な予測因子となります。
身体活動とエネルギー・栄養素について たんぱく質は身体活動量に応じて摂取
健康の保持・増進のためには、エネルギー収支バランスを適切に保ち、必要な栄養素を過不足なく摂取することが基本となります。また、身体活動量に応じてエネルギーや栄養素の必要量が変動します。
まとめ
2回にわたり「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」についてご紹介しました。ガイドは、ツールの見やすさ等も考慮されており、管理栄養士や健康運動指導士などの健康づくりに関わる専門家にとって活用しやすいものとなっています。
参考文献
関連コラム 糖尿病とは?合併症予防のための食事療法と運動療法~後編②~ 筋トレ中の方は必見!筋力アップのためのたんぱく質の摂り方