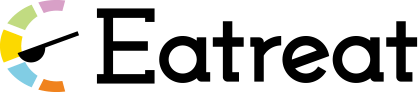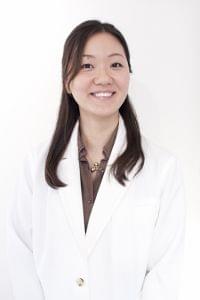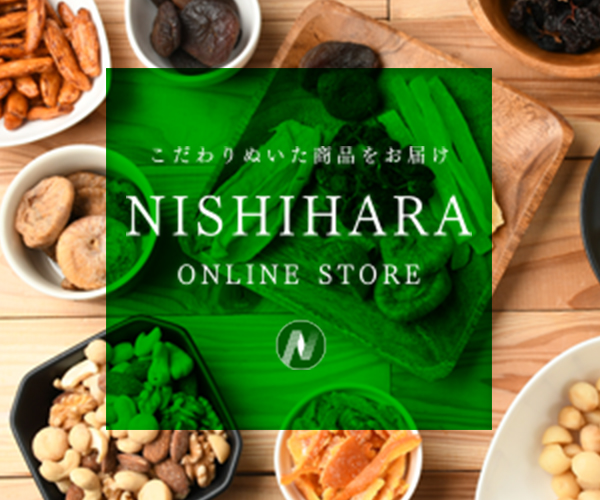漢方医学と中医学
漢方は、中国で東漢時代末期に張仲景という医学家によって書かれた「傷寒論」に記されている症状と方剤の症例を基本に、日本独自に発展してきた医学です。
症状に対して実践的にお薬を選びます。医師の熟練度によって処方が大きく異なります。
一方、中医学(中国伝統医学)は、「弁証論治(べんしょうろんち)」と言って病氣の原因やメカニズムなどを追及し、「証」を決定して治療方針を立てるのが特徴です。医師による診断のばらつきも漢方ほど大きくありません。
葛根湯は中国にはない?
日本で漢方の代名詞と言われるほど有名な「葛根湯」は、中国の街の薬局で見かけることはありません。傷寒論に「温病学」を組み合わせて発展してきた中医学では、あまり重要視されなかったという説がありますが、日本に馴染みやすい方剤だったのでしょう。
また、やけどや外傷などになど使われる万能クリームと呼ばれる「紫雲膏」は、江戸時代に花岡青洲(はなおかせいしゅう)という名医が作ったもので、当然中国では売られていません。(次回のコラムで、この紫雲膏の効能と作り方をご紹介します)。
血圧を下げるお薬として有名な「七物降下湯(しちもつこうかとう)」も昭和時代に日本で作られたものですし、婦人科でよく使う「女神散」も明治時代に日本で作られた新しい処方です。
他にも、中国で中医学を学んできた人間は知らない日本だけの処方も見かけます。
中医学も漢方も見るのは「ヒト」
「人間の體(からだ)は心を表現する器である」
「人間を離れた病氣というものはない」
と、心身一如の考えで人全体を見る医学としては同じです。
西洋医学をはじめ、中医学や漢方、アーユルヴェーダなどの伝統医学にはそれぞれの特徴と強みがありますので、自分に合った医療が選択できることが理想的ですね。
関連コラム
・薬膳料理と精進料理はどう違う?
・薬膳学と栄養学の違いと相性
・薬膳って何?