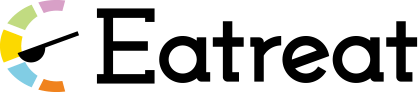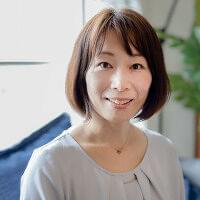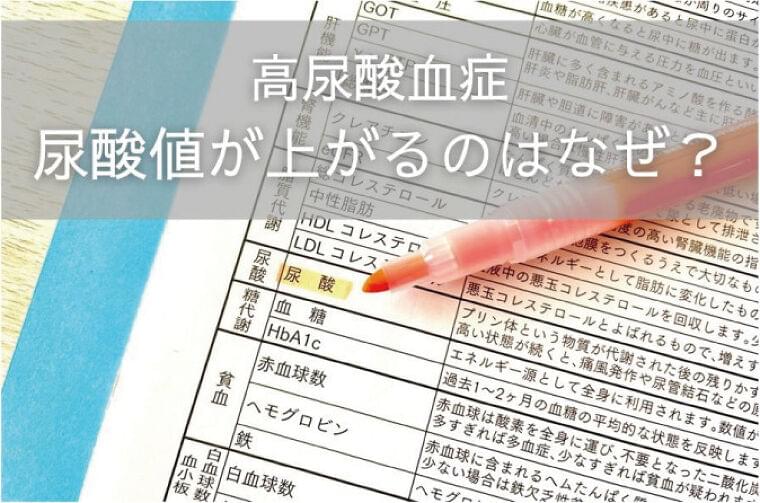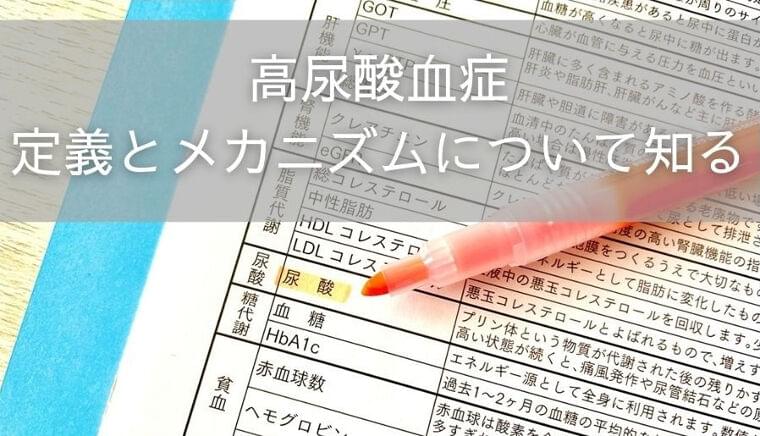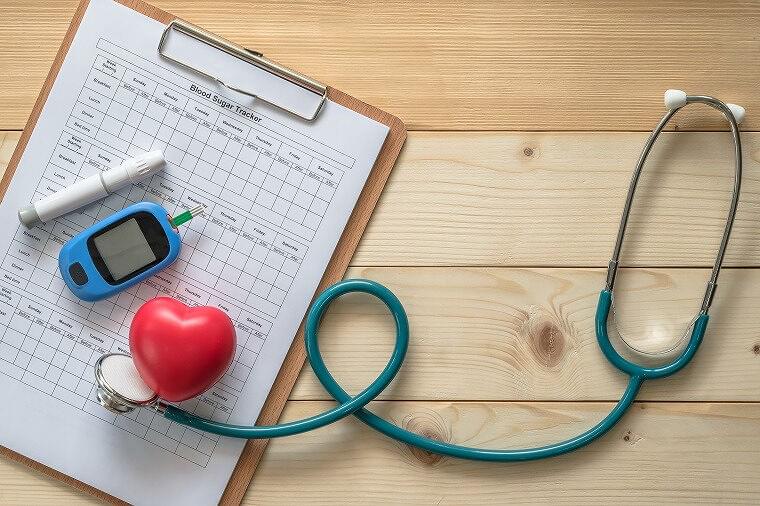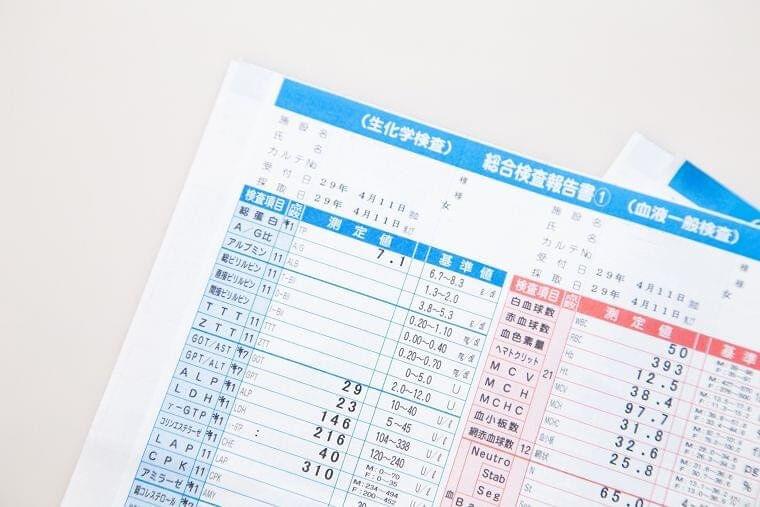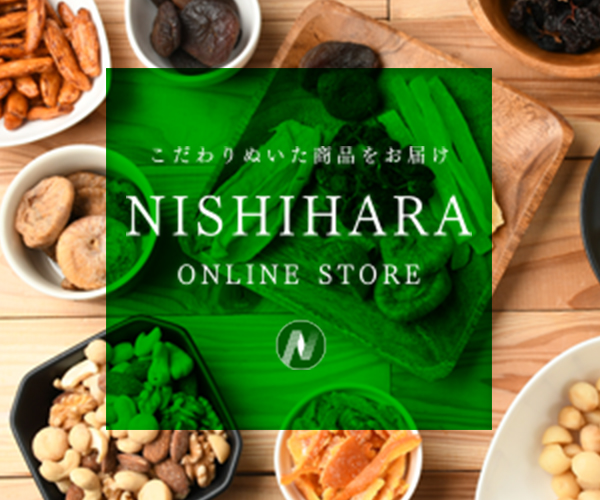「脂質異常症とは?」シリーズ最終回は、食事療法についてお伝えします。
本コラムでは、食事療法で求められるガイドラインに沿った食事療法についてまとめました。管理栄養士・栄養士が携わる現場での活用法も合わせてお伝えします。
基本の食事療法とは?
<基本の食事療法>
-
① 過食を抑え、適正体重を維持する
◆目標とする体重
18歳~49歳:[身長(m)]2×18.5~24.9 ㎏/m2
50歳~64歳:[身長(m)]2×20.0~24.9 ㎏/m2
65歳以上:[身長(m)]2×18.5~24.9 ㎏/m2
◆摂取エネルギーの目安
総エネルギー摂取量(kcal/日)=目標とする体重(kg)×身体活動量[軽い労作:25~30、普通の労作:30~35、重い労作:35~]
※高齢者は現体重に基づきフレイル、移動や入浴などの基本的なADL低下や併発症、体組成、身長の短縮、摂取状況や代謝状態の評価を踏まえ適宜判断する
-
② 肉の脂身、動物脂(牛脂、ラード、バター)、乳製品の摂取を抑え、魚、大豆の摂取を増やす
◆飽和脂肪酸のエネルギー比率として7%未満
-
③ 野菜、海藻、きのこの摂取を増やし、果物やナッツ類を適度に摂取する
◆食物繊維総量として25g/日以上を目安とする
-
④ 精白された穀類を減らし、未精製穀類や麦などを増やす
◆食物繊維総量として25g/日以上を目安とする
-
⑤ 食塩を多く含む食品の摂取を控える
◆6g/日未満
-
⑥ アルコールの摂取量を減らす
◆純アルコール量として25g/日以下
食事療法で期待される効果とは?
食事療法で期待される効果は、以下の3つが挙げられます。
・動脈硬化性疾患の予防と治療
・脂質異常症、高血圧、2型糖尿病の発症の予防と治療
・メタボリックシンドロームの予防と治療
総エネルギー摂取量と脂肪エネルギー比率の適正化は、高LDL-C血症や高TG血症の改善に有効です。また、食物繊維は、総コレステロールやLDL-C、non-HDL-Cを低下させる効果が知られています。
脂と油 あぶらの質と量
基本の食事療法の中で②にもあげたように、脂質異常症の食事療法では、あぶらの量だけでなく質もとても重要です。肉の脂のような飽和脂肪酸(脂)をとりすぎないようにして、できる限り魚油や植物性の油のような不飽和脂肪酸(油)に置き換えることが推奨されます。
脂肪のエネルギー比率は20~25%が目安ですが、飽和脂肪酸のエネルギー比率は7%未満が目標となっています。
脂肪酸の種類については、こちらのコラムを参考にしてください。
「脂肪酸の種類と動脈硬化について知る~脂質異常症とは?②~」
また、不飽和脂肪酸を増やす際には、エネルギーが過剰にならないように配慮することも大切です。その他、マーガリンやショートニング、ファットスプレッドを使用した菓子や揚げ物などの加工食品に多く含まれるトランス脂肪酸は、LDL-Cを上昇させ、HDL-Cを低下させることが分かっており、摂取量には注意したい脂です。
飽和脂肪酸のエネルギー比率7%未満について考える

一般的に、飽和脂肪酸は、肉の脂身やバターなどの乳製品、ココナッツ油やパーム油などに多く含まれます。例えば、鶏むね肉(皮付き)の飽和脂肪酸は、100g中2.6g(エネルギー比率は20%)に対し、鶏むね肉(皮なし)の飽和脂肪酸は、100g中0.23g(エネルギー比率4%)です。合いびき肉を使用したハンバーグが主菜の場合は、エネルギーが過剰にならないように配慮しつつ、主食や副菜で飽和脂肪酸を控えた献立にすることで、飽和脂肪酸エネルギー比率を低下させることができます。
まとめ
5回にわたり「脂質異常症」についてご紹介しました。
食事療法では、基本に沿った上で対象者ごとの課題を修正し、前向きに長期的に取り組めるような無理のない支援であることも大切です。
参考文献
・一般社団法人 日本動脈硬化学会:「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド2023年版」、(2023年)
関連コラム
・高血圧症とは? 定義とメカニズムを知る
・肥満症とは?肥満の定義とメカニズムを知る